初めに、このページは以前「忍者の町 甲賀」として公開されていたものを一部配置などを見直しての一部を復元したものである。
誤りなど発見した場合@mokunojouまで
誤りなど発見した場合@mokunojouまで
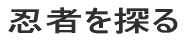
甲賀流忍術は伊賀流と並んで有名である。しかし、伊賀流には服部半蔵、百地三太夫など著名な忍者がいるのに甲賀流にはスターがいない。これは隠密という忍者の特性からくることもあるが、それよりも忍者に対する認識の違いが大きいのではないかと思われる。実際の忍者の実像はあの派手な術を使うninjaとは大きな隔たりがあり、戦国期に甲賀の侍たちが己を忍者と思っていたかどうかさえ疑わしい。忍者は江戸時代以降の創作ではないかと考えられる。
それでも甲賀地域において忍者とおぼしき人物をあげるとすると、それは居住地の近隣に城を構えた土豪層である。彼らは弱小であったから地域的連合である「甲賀郡中惣」に加わって団結していた。戦国期に弱肉強食の道を歩まず連合によって自らを守ろうとしたところに甲賀侍の特徴がある。甲賀21家とか53家などというから、かなりの数の連合である。その中に大原氏があり、そこから分かれた篠山氏があった。このような甲賀の侍たちが甲賀忍者の主役であると考えてそう間違いではなかろうと思う。彼らは伊賀忍者の階層からいうと中忍にあたる。その下に手足となる下忍の間者がいたであろうが、これは歴史にあらわれない。
甲賀侍は、近江の守護佐々木氏(六角氏)や信長、秀吉、家康などとの関わりで、時に辛酸をなめ、いくども浮沈を繰り返しながら戦国期を乗り切っている。彼らがどこから来て、どんな活動をしたのかを、大原氏の系譜を辿りながら明らかにしていきたい。郷土の歴史から日本の歴史を見るという視点を大事にしたい。それがこのHPの目的である。
歴史史料はすべてが正しいとはいえない。系図にいたってはむしろ捏造だらけといえるだろう。江戸時代に幕府は御家人に系図の提出を求めた。さしたる家系を持たぬ御家人は困って系図屋に頼んで書いてもらったそうである。それが寛永諸家譜であり寛政重修諸家譜である。史料の考証は江戸期の系図屋との知恵比べの趣がある。系図の信憑性を検証しながら、人物を通して「甲賀忍者」の実像に迫りたい。しかし、乏しい史料でかなり断定的な見方をしているのではないかと思う。間違いを指摘してくだされば誠にありがたい。
| 氏 名 | 摘 要 |
|---|---|
| 伴 善男 | 平安朝の大納言。大原氏などの祖とされるが、はたして事実かどうか。 |
| 三河伴氏 | 伴善男の子孫とされる一族である。員助は幡豆郡司、依助は三河大介である。資兼は源義朝につき清原家衡を討つ。俊実は富永又は設楽を名乗り保元の乱に加わる。大原氏のルーツである。 |
| 伴 資乗 | 安芸守。設楽を名乗る。「闘争して人を殺害し、三河国を去りて近江国に漂泊す。」(寛政重修緒家譜)。三河と大原を結ぶ人物である。 |
| 大原貞景・盛景 | 資乗の子。三河国を退去し近江国甲賀郡大原邑に住し、伴太郎資業をあらためて大原八郎貞景と称す。盛景は弟で、三郎と称する。この二人が大原氏の祖である。 |
| 毛枚氏と山岡氏 | 毛枚景広は貞景の4代後裔で甲賀の毛枚に住し、毛枚氏を称する。別名毛枚太郎。その子孫が山岡氏となる。 |
| 山岡景隆 | 資広の代になり田上の城、勢多の山田岡の城に住し、山岡姓を名乗る。景隆・景友、江南の旗頭として大活躍する。信長秀吉家康との関わりに注目。 |
| 滝川一益 | 一益は甲賀武士の出であるか。それとも紀氏か。甲賀武士から見れば裏切り者であるが、興味深い人物である。 |
| 大原篠山氏 | 甲賀侍のうち大原篠山氏に焦点を当てる。篠山氏は大原氏の分かれである。城を築くと独立して姓を改めることがしばしば見られる。 |
| 大原為家(源三) | 大原盛景の3代後裔。甲賀21家の一。源三の子孫に加津井氏(勝井氏)がある。 |
| 篠山景春 | 大原から笹山(父景元の代)、篠山(景春の代)に改姓。代々鳥居野を領す。伏見の篭城戦で子景尚とともに戦死する。子孫は鳥居野の領主及び江戸城警護の甲賀組の一員となるl。 |
| 篠山諸士 | 篠山氏を4系統に分け代々の諸士を瞥見する。景尚、景義、景徳、資門、資忠他。 |
| 篠山景義 | 景尚の子孫。景春から数えて9代目。大阪西成代官、佐渡奉行を歴任。 |
| 篠山景徳 | 景義の子[養子)。佐渡奉行、大目付など歴任。忍者の子孫が大名を監察する大目付になるとは驚きである。 |
| 篠山資門・具晴 | 資盛から数えて3代目。家督を二人の兄弟に分譲する。鳥居野お姫山に石碑がある。 |
| 笹山資忠 | 笹山監物。篠山景春の叔父。大原数馬家の祖。数馬家系図では景春の兄となっている。 |
| 大原数馬 | 今も残る城跡に居住する郷士の名門。多くの史料を保存されている。篠山氏と何代にも及ぶ縁戚関係にあり、幕末維新には東征軍に加わる。 |