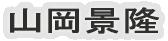
勢多城を築き名称も山岡と改称した資広から後の系図は、
資広――景長――景秀――景昌――景綱――景就――景之――[景隆]――景以
と続く。そして、景隆の弟が景友(道阿弥)である。資広以降、代々勢多城に住し佐々木家の家臣的な地位について「江南の旗頭」の役を受け持っている。景之の妻は和田伊賀守維政の娘である。(即ち景隆の母は和田氏の出))
永禄12年織田信長が三好義継を討つとき、景隆に味方に加わるよう誘いをかけたが、これを断ったため攻められて柳生に敗走することがあった。しかし、その後和を乞い信長の先鋒として松永久秀と戦うこととなった。その時のエピソードを紹介しよう。戦いの厳しさと情けがよく出ている。
「久秀 景隆が女を虜りて城門の外に置、景隆をして進まざらしむ。景隆士卒に下知してわが女をまず射殺すべしというふ。よりて兵士等矢石を放つといへども、あたらず。久秀終に敗軍し、降を請。右府(信長のこと)景隆の軍功を感賞ありて本領を与えらる。後久秀彼女をかへし送らんといふ。景隆いはく、女ながら敵に生け捕らるるうへは、わが子にあらずと、ここにをいて久秀家臣渡辺左馬助重に嫁せしむ。」(山岡系図)
その他の景隆出陣等事績を箇条書きでかく。
- 永禄12年 伊勢大河内城攻め
- 天正元年 宇治真木嶋の義昭軍を破る。
- 天正元年 朝倉義景を近江地蔵山に攻める。
- 天正3年 勢多橋を作る。
- 天正9年 伊賀国阿拝郡に兵を発し、河合、木興、壬生野の3城をおとす。
- 天正10年 明智光秀謀反の時勢多橋を焼いて進路を閉ざす。坂本城を攻める。
- 天正10年 家康帰国の危難を、勢多より信楽音聞峠(お斎峠)までお供をして一揆を打ち散らし導く。
- 天正11年 秀吉により勢多城を追われ毛枚邑に幽居す。(勝家に与し、ひそかに志を東照宮に寄せたため)。
- 天正13年 毛枚にて死す。61歳。
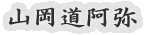
景隆の弟 権大僧都 園城寺光浄院第5代住持
将軍義昭に仕え頭角を顕す。義昭が信長に叛してより一時石山寺に篭城したが、光秀、勝家の説得で退城する。以後還俗して景友を名乗り、信長に臣従する。本能寺の変の後は織田信雄に従い秀吉と対立した。その後剃髪し道阿弥を号す。
関が原合戦では家康側につき活躍。伏見篭城戦では甲賀侍を動員し、戦死した甲賀侍の処遇にも関わった。家康は道阿弥に九千石を与え、内四千石は江戸城警護役としての甲賀組に宛行った。甲賀組には伏見篭城戦で戦死した甲賀侍の子息が多く採用された。こうして騎兵十人歩卒百人が江戸に赴き江戸城表門の警護の任に当たることになった。甲賀侍の中には道阿弥の指導的立場をよく思わず郷士として甲賀に留まる者もいた。道阿弥の後は景以が引き受けている。
将軍義昭に仕え頭角を顕す。義昭が信長に叛してより一時石山寺に篭城したが、光秀、勝家の説得で退城する。以後還俗して景友を名乗り、信長に臣従する。本能寺の変の後は織田信雄に従い秀吉と対立した。その後剃髪し道阿弥を号す。
関が原合戦では家康側につき活躍。伏見篭城戦では甲賀侍を動員し、戦死した甲賀侍の処遇にも関わった。家康は道阿弥に九千石を与え、内四千石は江戸城警護役としての甲賀組に宛行った。甲賀組には伏見篭城戦で戦死した甲賀侍の子息が多く採用された。こうして騎兵十人歩卒百人が江戸に赴き江戸城表門の警護の任に当たることになった。甲賀侍の中には道阿弥の指導的立場をよく思わず郷士として甲賀に留まる者もいた。道阿弥の後は景以が引き受けている。
(以下復活者の補足)
伏見籠城の子孫は関ケ原の戦いの後甲賀郡内に知行所を拝領しそのまま甲賀に留まっている。彼ら甲賀衆が江戸に行くのは寛永9年になってからで、その時には山岡景以を組頭とし桜田門番となり、その後水口御殿門番を経たのち寛永21年から鉄砲百人組として江戸城大手三之門番を勤めることとなる。
伏見籠城の子孫は関ケ原の戦いの後甲賀郡内に知行所を拝領しそのまま甲賀に留まっている。彼ら甲賀衆が江戸に行くのは寛永9年になってからで、その時には山岡景以を組頭とし桜田門番となり、その後水口御殿門番を経たのち寛永21年から鉄砲百人組として江戸城大手三之門番を勤めることとなる。


