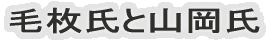
毛枚景広は貞景から数えて5代目に当たる。山岡系図には、
「太郎 左衛門尉
近江国甲賀郡毛枚邑に住す。よりて毛枚(もびら)をもって称号とす。のち景政にいたるまでおなじ。」
としている。
また、それより以前に編纂された寛永諸家譜には、
「その(貞景)末孫毛枚太郎景広、大原の庄毛枚村の山間に舘をかまふ。これによりて人みな山岡の名をよぶ。子孫のいみなにみな景の字をもちひて首にをく。景行天皇の末流をしらしめんがためなり。」
「太郎 左衛門尉
近江国甲賀郡毛枚邑に住す。よりて毛枚(もびら)をもって称号とす。のち景政にいたるまでおなじ。」
としている。
また、それより以前に編纂された寛永諸家譜には、
「その(貞景)末孫毛枚太郎景広、大原の庄毛枚村の山間に舘をかまふ。これによりて人みな山岡の名をよぶ。子孫のいみなにみな景の字をもちひて首にをく。景行天皇の末流をしらしめんがためなり。」

今に残る山岡城跡を訪ねた。
県道から程近い所ではあるが急峻な細い坂道を上りきったところに岡本氏邸があり、その裏に城跡が認められた。
天然の要害を利用して防備の備えを図っている。眼下に毛枚が一望できる高台である。
県道から程近い所ではあるが急峻な細い坂道を上りきったところに岡本氏邸があり、その裏に城跡が認められた。
天然の要害を利用して防備の備えを図っている。眼下に毛枚が一望できる高台である。
貞景――景重――景光――信遍(のぶゆき)――[景広]――景範
景広の子供に景範、貞広、景忠がいて、山岡氏に続く家系は、山岡系図では景範であるが、貞広としている系図もある。また、景忠は、
「甲賀郡上野邑に住するにより、毛枚を改めて上野を称す。子孫繁茂して二十余家となる。」
と記されている。南北朝期活躍する上野氏は、毛枚氏の分かれである。
「甲賀郡上野邑に住するにより、毛枚を改めて上野を称す。子孫繁茂して二十余家となる。」
と記されている。南北朝期活躍する上野氏は、毛枚氏の分かれである。
毛枚氏から山岡氏への系図は、
景範(毛枚氏)――広政――景政――景通(大鳥居氏)――景久――景以(かげもち)――資広(山岡氏を称す。景広ともいう。)――景長
山岡氏の始祖景広については、諸家譜に
「近江国田上の城に住し、永享年中同国栗太郡勢多邑を討取、初めて勢多の山田岡に城を築きてこれに移る。この時一字を略して山岡の二字を用いて称号とす。後勢田城を嫡男景長に譲り、石山の古城を営みてこれに住し、剃髪して光浄院と号す。嘉吉2年(1442)死す。」
「近江国田上の城に住し、永享年中同国栗太郡勢多邑を討取、初めて勢多の山田岡に城を築きてこれに移る。この時一字を略して山岡の二字を用いて称号とす。後勢田城を嫡男景長に譲り、石山の古城を営みてこれに住し、剃髪して光浄院と号す。嘉吉2年(1442)死す。」

山岡景以の墓碑
右の墓は毛枚にあり、「山岡主計頭景以之墓」と読める。景以は二人いて、一人は上の系図に見える大鳥居氏の時代の人であり、もう一人は景隆の末子である景以である。この墓碑は後者である。彼は叔父道阿弥(景友)の跡をついで3000石を宛行われた。また、毛枚が山岡氏のルーツであることは、山岡景隆の最期が毛枚の地であったことでも頷ける。
右の墓は毛枚にあり、「山岡主計頭景以之墓」と読める。景以は二人いて、一人は上の系図に見える大鳥居氏の時代の人であり、もう一人は景隆の末子である景以である。この墓碑は後者である。彼は叔父道阿弥(景友)の跡をついで3000石を宛行われた。また、毛枚が山岡氏のルーツであることは、山岡景隆の最期が毛枚の地であったことでも頷ける。
現在、山岡会が2年に1回ぐらい臨湖庵で開かれているそうである。臨湖庵は瀬田川沿いの勢田城跡とされる場所にあり、遺跡も少し残っているそうである。子孫の方々は時に毛枚の城跡にも来られると聞いている。


