
大原氏
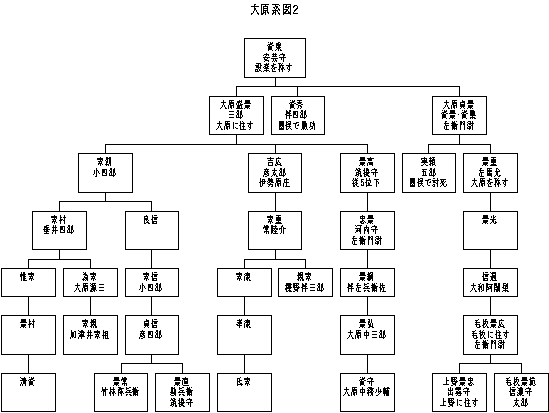
篠山氏は大原氏の一族で南山六家に属している。系図では、先祖は大伴氏であるという。大伴氏とは古代の大氏族の一つで、神話時代の天忍日命から始まり道臣命、大伴金村と続く。壬申の乱では大海人皇子の側につき家運を回復し大納言にまで昇進し、一時は藤原氏と拮抗する勢力を持った。しかし、応天門の火災の罪をきた大納言伴善男が伊豆に流されてから衰えた。この伴善男の末裔と名乗る氏族が三河や近江に多く、大原氏もその一つである。
大原氏は、寛政重修諸家譜によると次のように書かれている。
「家伝に、先祖大原備後守盛景近江国甲賀郡に住す。その子孫竹林を称し、景時にいたりて大原に復すといふ。今旧家伴氏山岡の譜を按ずるに大伴連は道臣命4世の孫、狭手彦の後なり。大伴宿禰国道の時、淳和天皇の御諱をはばかり改めて伴の朝臣となる。三河大介資兼より4代安芸権守資乗が3男八郎貞景、近江国甲賀郡大原に住して大原を称すといひ、貞景が弟を大原三郎盛景とす。これ家伝にいふ備後守と同人たるべし。」
「家伝に、先祖大原備後守盛景近江国甲賀郡に住す。その子孫竹林を称し、景時にいたりて大原に復すといふ。今旧家伴氏山岡の譜を按ずるに大伴連は道臣命4世の孫、狭手彦の後なり。大伴宿禰国道の時、淳和天皇の御諱をはばかり改めて伴の朝臣となる。三河大介資兼より4代安芸権守資乗が3男八郎貞景、近江国甲賀郡大原に住して大原を称すといひ、貞景が弟を大原三郎盛景とす。これ家伝にいふ備後守と同人たるべし。」
また、貞景の経歴について、鎌倉幕府中央との関係がよく分かる記述がある。(山岡系図)
「貞景 或資景 初資業 或資奈 伴太郎 八郎 五郎大夫 左衛門尉
三河国を退去し、近江国甲賀郡大原邑に住し伴太郎資業を改めて大原八郎貞景と称す。よりて俗其邑を呼で伴里といふ。建仁3年6月佐々木左衛門尉定綱等鎌倉よりの命を受け、阿野法橋全成が男播磨公頼全を穿ちもとむ。貞景是時定綱に属し、頼全東山の延年 寺に住するのよしをきき、彼地にはせむかひこれを誅す。」
「貞景 或資景 初資業 或資奈 伴太郎 八郎 五郎大夫 左衛門尉
三河国を退去し、近江国甲賀郡大原邑に住し伴太郎資業を改めて大原八郎貞景と称す。よりて俗其邑を呼で伴里といふ。建仁3年6月佐々木左衛門尉定綱等鎌倉よりの命を受け、阿野法橋全成が男播磨公頼全を穿ちもとむ。貞景是時定綱に属し、頼全東山の延年 寺に住するのよしをきき、彼地にはせむかひこれを誅す。」
少し解説すると、定綱は、源平合戦の立役者秀義の長男。近江佐々木庄が本領であるが、平治の乱後、父秀義に連れられ相模渋谷庄に寄留し、治承4年の頼朝挙兵に兄弟そろって応じ、鎌倉幕府の重鎮となり、近江守護に任ぜられた人物である。また、阿野全成は、源義朝の子、義経の兄で、母は常盤御前。頼朝が石橋山で挙兵した時参戦している。にもかかわらず建仁3年(1203)5月に謀反の疑いをかけられて召し捕られ、6月23日に殺された。
頼家が殺させたとなっているが、北条氏の謀略と考えられている。上の資料にみえる全成の子頼全が京都で殺されたのは、同年7月16日であり、上の資料の6月と異なるが、貞景が佐々木定綱の命に服して頼全を殺したのは真実であろう。北条氏→佐々木氏→大原氏の主従関係が読み取れる。
その後の大原氏の活躍を系図から見ると、貞景の子実景、実頼は承久3年の乱に官軍に属して尾張墨俣で討ち死にしている。しかし、貞景の兄の資秀は幕府側で先陣を進み宇治川で右目を射たれて負傷し、勲功を賜っている。(この時佐々木氏も2派に分かれて戦っている。実景らは定綱の長子広綱の軍に加わって敗戦の憂き目を見たのであろう。4男の佐々木信綱側は幕府側で戦功をあげ、佐々木氏を継いでいる。
また、貞景の弟盛景の子景高は、将軍義詮に仕え、延文5年(1360)仁木左京大夫義長が将軍に叛いたとき、一族160騎が葛城山に陣して奮戦。この時将軍義詮から「感武功」で、太刀一振を賜っている。
篠山氏
篠山系図において、資乗は設楽六郎太夫ともいい、三河大介、安芸守としている。また貞景は大原太郎、盛景は大原三郎である。この末弟に家朝(大原小四郎)がおり、その子良信の系統が篠山氏である(系図参照)。ところが篠山の先祖については大原系図や勝井系図では良信の弟家村(垂井四郎)の系統に位置づけている。
真偽詮索は措いて、大原氏と同様に寛政重修諸家譜を引用する。
「家伝に、大原八郎貞景が弟三郎盛景より7代蔵人頭景元、大原を改めて笹山を称す。その男理兵衛景春笹文字を篠に改む。其男彦十郎景尚慶長2年より東照宮につかえたてまつり、5年伏見城に籠りて戦死す。その男弥次兵衛景末父討死の時襁褓(きょうほう=幼児)のうちにありて、母と共に近江国甲賀郡の山中にあり。のち江戸に召され、山岡主計頭景以が組に属し、百人組の与力となる。それより景義まで7代連綿して百人組の与力を勤むといふ。(後略)」
「家伝に、大原八郎貞景が弟三郎盛景より7代蔵人頭景元、大原を改めて笹山を称す。その男理兵衛景春笹文字を篠に改む。其男彦十郎景尚慶長2年より東照宮につかえたてまつり、5年伏見城に籠りて戦死す。その男弥次兵衛景末父討死の時襁褓(きょうほう=幼児)のうちにありて、母と共に近江国甲賀郡の山中にあり。のち江戸に召され、山岡主計頭景以が組に属し、百人組の与力となる。それより景義まで7代連綿して百人組の与力を勤むといふ。(後略)」
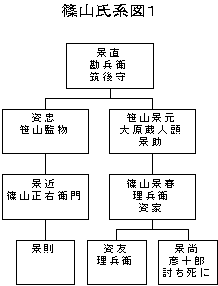
 篠山家の馬印 |

このように諸氏の系図に違いがあり、実証はできないが、景春の祖父景直のとき
「・・大原庄住居於鳥居野村構小城・・」(篠山氏系図)
とあるので、既に篠山城は造られていたであろう。姓を大原から笹山に代えたのは、父の景元(大原蔵人)のときで、大原氏系図には元亀2年(1571)とある。年代からみて無理はない。
「・・大原庄住居於鳥居野村構小城・・」(篠山氏系図)
とあるので、既に篠山城は造られていたであろう。姓を大原から笹山に代えたのは、父の景元(大原蔵人)のときで、大原氏系図には元亀2年(1571)とある。年代からみて無理はない。
篠山氏にとって災難だったのは秀吉の天下取りへの動員である。篠山景春は甲賀士36人と一緒に織田信長に仕えていたが、信長死後羽柴筑前守に属し、尾州長久手で信雄と秀吉の合戦(天正12年4月)のおり、信雄と「通心」した疑いをかけられ失脚した。信雄は信長の子供であるから、そんな疑いをかけられたのであろう。それで関地蔵辺りに隠れ住むことになった。
篠山氏だけではない。他の甲賀武士もひどい目に合っている。天正13年(1585)、秀吉は前年の小牧長久手の戦いで家康と組んだ紀州の根来・雑賀の一揆を鎮圧するのに、甲賀武士も動員して水攻めの堤を築かせた。それが不備であったと難癖をつけて領地没収を命じたのである。大方の甲賀武士は仕方なく命に服したが、小佐治の佐治氏は勇敢にもこれに抗して戦った。だが、結果は水口古城(岡山城)の堀 秀政・中村一氏に攻められ滅亡している。篠山氏では、景元の弟資忠(篠山監物)は領地を没収され「住所離散」の憂き目に遭い、後、相模に移ったと記されている。資忠の子景近は田堵野に住し、これが大原数馬氏のご先祖である。このようにして甲賀武士から領地を奪い、それを水口古城の領主に集中させ、集権的支配を拡大していった。こうして天正13年(1585)には岡山城の中村一氏は6万石の大名になり、天正18年(1590)に一氏移封のあとは増田長盛、更に文禄4年(1595)からは長束正家が城主を引き継いだ。
これらの不運を取り払ってくれたのが家康である。慶長年中に家康が上洛の道すがら景春を召し出して先祖のことや「年来の在様」を聞き、近隣十郷の代官をするよう命じている。篠山氏がどれだけ恩義を感じたか想像に余りある。
そして、この恩義は、数年後家康の危機を救うことになる。慶長5年、家康が上杉中納言景勝を討つために甲賀郡を通過しようと石部に宿をとっていた時に、景春は、秀吉政権の五奉行の一人長束大蔵大輔が水口駅で陰謀を企てている事を知らせた。家康は長束からの朝餉の招待をすっぽかして夜中に宿を発ち、無事水口を通過し関に着いている。景春はその時褒美として「腰物」をもらった。いかにも忍者らしい働きである。事の真否は知る由もないが、家康は無事水口を通過し上杉攻めに向かうことができ、直後の関ヶ原の戦いで勝利して天下を取り、江戸時代の350年が続くのである。正に「情けは人のためならず」である。余談であるが、事後長束はこの企みを否定したが、家康は信じなかったという。
<改正三河後風土記>
「18日(慶長5年6月)の昼頃には大津城に着かせ給ひ今夜は石部を以て御旅館となさる。長束大蔵大輔正家水口より参上し拝謁し、明朝は居城にて朝餉を進られたし立ち寄らせ給わん事を願ふ云々。然るに其夜戌の刻俄かに石部を立たせ給ひ、夜中水口を過ぎさせ給ふとて渡辺忠右衛門御使いとして長束方へ遣わされ云々。今夜(19日)は関の地蔵に御止宿あり。実にや昨夜長束石部へ参詣して後、その地の代官篠山理兵衛参上し、長束明朝君を水口城に招請し奉るとて夥しき用意の様不審少なからずと雑説区々にて候へば明朝水口立寄は御延引有って然るべしと密々告げ奉る云々。夜中篠山理兵衛御道案内し吉川半兵衛宗春、土屋惣右衛門其外近習少々御共にて石部より間道を経て土山まで至らせ給ひしと也。」
1カ月後の慶長5年7月、石田三成は挙兵し伏見城を守る鳥居元忠を攻める。この籠城戦では、景春・景尚父子をはじめその家臣は多くの甲賀武士と共に戦死する。墓は鳥居野の多聞寺にあり、大切に葬られている。親子共に戦死した篠山氏の子孫がどうなったか気になることであるが、家康の功労者に対する処置は誠に温かい。家督は彦十郎の弟資盛(資友、理兵衛、甚吉)が継いで旗本として鳥居野を領有し、篠山氏の本流(景尚の子孫)は江戸に移り、中には幕府の要職について活躍した方もいる。(江戸時代の章参照)
1カ月後の慶長5年7月、石田三成は挙兵し伏見城を守る鳥居元忠を攻める。この籠城戦では、景春・景尚父子をはじめその家臣は多くの甲賀武士と共に戦死する。墓は鳥居野の多聞寺にあり、大切に葬られている。親子共に戦死した篠山氏の子孫がどうなったか気になることであるが、家康の功労者に対する処置は誠に温かい。家督は彦十郎の弟資盛(資友、理兵衛、甚吉)が継いで旗本として鳥居野を領有し、篠山氏の本流(景尚の子孫)は江戸に移り、中には幕府の要職について活躍した方もいる。(江戸時代の章参照)
伏見籠城戦
*滋賀県史によると、
「(前略)その発端として伏見城の攻撃開始せられ、包囲十余日の後松の丸の守兵中甲賀武士等正家に内応して放火し、城遂に陥落した。(後略)」
「(前略)その発端として伏見城の攻撃開始せられ、包囲十余日の後松の丸の守兵中甲賀武士等正家に内応して放火し、城遂に陥落した。(後略)」
*甲賀郡志も、その間の事情を詳しく書いている。
「(前略)6月18日、大阪の兵伏見城を囲む。山岡景友急を諸士に告げ馳せ来たらしむ。29日、諸士同城内松丸に入りて拒守す。時に増田長盛重臣福原清左衛門をして謂はしむ。曰く子等心を悛(あらた)め主公に属せば領地旧の如くせん。然らずんば一撃のもとに殪(たお)し併せて妻子を殺すであろう。数刻を期して去就を決めよ。(中略)8月1日伏見城陥る。同日篠山、竹林等の一族部下戦没せるもの31人、他の負傷者は悉く郷里に帰る。一書に此時伏見城にて叛を謀り敵を誘い入れたる永原十内、山口宗助ならびに甲賀士18人の者は追捕せられ粟田口に於て磔せらるといふ。(後略)」
「(前略)6月18日、大阪の兵伏見城を囲む。山岡景友急を諸士に告げ馳せ来たらしむ。29日、諸士同城内松丸に入りて拒守す。時に増田長盛重臣福原清左衛門をして謂はしむ。曰く子等心を悛(あらた)め主公に属せば領地旧の如くせん。然らずんば一撃のもとに殪(たお)し併せて妻子を殺すであろう。数刻を期して去就を決めよ。(中略)8月1日伏見城陥る。同日篠山、竹林等の一族部下戦没せるもの31人、他の負傷者は悉く郷里に帰る。一書に此時伏見城にて叛を謀り敵を誘い入れたる永原十内、山口宗助ならびに甲賀士18人の者は追捕せられ粟田口に於て磔せらるといふ。(後略)」
*改正三河後風土記
「(前略)7月15日(慶長5年)の早天浮田中納言秀家総大将にて大阪を進発す。総勢3万9千余伏見に着陣し攻口の手配りし(中略)長束正家計を案じ出し守勢の中に浮貝藤助とて甲賀の者ありしかばこの者に秘計を授け松丸に籠りたる甲賀者の中に山口宗助、永原十内両人へ矢文を遣はして其方とも申し合わせ回忠して城内へ火を放ち内応し寄せ手を引き入れば秀頼公より莫大の恩賞あるべし。此事同意せざるにおいては故郷に残しおく妻子眷属悉く磔に行はるべしと申させければ、此者とも大いに驚き甲賀四十余人申合せ明夜亥子の刻城内に火を掲げて内応すべしと返答す。(中略)城兵は内通の者ありとは知らず唯力を尽くし防戦す。松丸を守りし城兵は内より甲賀の者所所に火を放って裏切りし、外よりは寄せ手大勢にて乱入すれば防ぎ兼ねて、岩間兵庫上林竹庵と討ち死にし深尾清十郎生け捕られ、佐野肥後守は大筒を放って防ぎしが大筒裂けて焚死す云々。(中略)伏見城にて反逆し敵を引き入れし永原十内、山口宗助並びに甲賀18人の者どもは追捕せられ粟田口にて磔にかけらる。(後略)」
「(前略)7月15日(慶長5年)の早天浮田中納言秀家総大将にて大阪を進発す。総勢3万9千余伏見に着陣し攻口の手配りし(中略)長束正家計を案じ出し守勢の中に浮貝藤助とて甲賀の者ありしかばこの者に秘計を授け松丸に籠りたる甲賀者の中に山口宗助、永原十内両人へ矢文を遣はして其方とも申し合わせ回忠して城内へ火を放ち内応し寄せ手を引き入れば秀頼公より莫大の恩賞あるべし。此事同意せざるにおいては故郷に残しおく妻子眷属悉く磔に行はるべしと申させければ、此者とも大いに驚き甲賀四十余人申合せ明夜亥子の刻城内に火を掲げて内応すべしと返答す。(中略)城兵は内通の者ありとは知らず唯力を尽くし防戦す。松丸を守りし城兵は内より甲賀の者所所に火を放って裏切りし、外よりは寄せ手大勢にて乱入すれば防ぎ兼ねて、岩間兵庫上林竹庵と討ち死にし深尾清十郎生け捕られ、佐野肥後守は大筒を放って防ぎしが大筒裂けて焚死す云々。(中略)伏見城にて反逆し敵を引き入れし永原十内、山口宗助並びに甲賀18人の者どもは追捕せられ粟田口にて磔にかけらる。(後略)」
以上伏見籠城戦に関する資料を三点紹介した。真実と異なる点もあるであろうが、甲賀忍者の姿が浮かび上がり興味深い。どちらに与したとしても、それは責められるべきものではない。敵の情勢を探りそれを作戦に生かすことは当時の武将の力量であり、今川方の鵜殿長持攻めに甲賀忍者が傭兵として活躍した例もある。
慶長5年(1600)6月、伏見城籠城戦では、景春・景尚父子をはじめその家臣は多くの甲賀武士と共に戦死する。墓は鳥居野の多聞寺にあり、大切に葬られている。親子共に戦死した篠山氏の子孫がどうなったか気になることであるが、家康の功労者に対する処置は誠に温かい。江戸時代になってからその子孫は旗本として鳥居野を領有し、篠山氏の本流は江戸に移り、幕府の要職について活躍した方もいる。9代目の十兵衛景義は佐渡奉行として活躍し、佐渡に大きな石碑があり、来歴等刻されている。10代の景徳は佐渡奉行として佐渡の一揆を鎮め、また、幕府の大目付として従5位下に叙せられている。
- 伏見籠城での戦死者
- 篠山理兵衛景春 篠山彦十郎景尚 杉井隆太郎政輔
- 永野宇右衛門忠孝 勝矢幸蔵英敦 和田忠五郎定治
- 岩田勝蔵英政 斎藤北郎芳昌 阿早田甚之丞安仁
- 阿部九郎左衛門直敏 小林三治郎政元 渡辺伝兵衛守信
その他の資料
<伏見籠城罷出候者>郡志より
芥川治右衛門 芥川治郎左衛門 芥川清右衛門 望月兵太夫 望月助太夫 池田九右衛門 岩室権六郎 上野市郎兵衛 大原勝治郎
佐治 10人、 神保 2人、 隠岐 16人、 山中 19人、 美濃部 4人、
芥川 8人、 鵜飼 25人、 望月 24人、 滝 11人、 池田 1人、
岩室 3人、 上野 14人、 大原 15人、 伴 10人、 和田 5人、
大野 4人、 服部 3人、 下郡 15人、 都合〆て人数190人
佐治 10人、 神保 2人、 隠岐 16人、 山中 19人、 美濃部 4人、
芥川 8人、 鵜飼 25人、 望月 24人、 滝 11人、 池田 1人、
岩室 3人、 上野 14人、 大原 15人、 伴 10人、 和田 5人、
大野 4人、 服部 3人、 下郡 15人、 都合〆て人数190人
以上の内戦死せし諸士の氏名
芥川治右衛門 芥川治郎左衛門 芥川清右衛門 望月兵太夫 望月助太夫
池田九右衛門 上野半九郎 上野長左衛門 上野長八郎 山岡権右衛門
大原民部 大原六輔 大原介市 大原長三郎
芥川治右衛門 芥川治郎左衛門 芥川清右衛門 望月兵太夫 望月助太夫
池田九右衛門 上野半九郎 上野長左衛門 上野長八郎 山岡権右衛門
大原民部 大原六輔 大原介市 大原長三郎
〜同日篠山、竹林等の一族部下戦没せる者31人、他の負傷者は悉く郷土に帰る。一書に此の時伏見城にて叛を謀り敵を誘い入れたる永原十内、山口宗助並びに甲賀士18人の者は追捕せられ粟田口にて磔せらるという。
<甲賀古士旧記>より
〜落城の砌十人之内、高峰新右衛門・梅田勝右衛門・篠山彦十郎・竹林左衛門九郎討死、百人之内、七十人斗討死仕候事
<山岡資料>栗東歴史民俗博物館紀要第3号 伏見籠城覚より
- *籠城討死之覚
- 高嶺新右衛門
- 同新右衛門(新右衛門の子、前の名茂兵衛と申候) 同新右衛門(茂兵衛子) 同左吉(新右衛門いとこ)
- 竹林左衛門佐
- 同左衛門九郎(左衛門佐子) 同権兵衛(左衛門九郎子) 同権左衛門(権兵衛いとこ)
- 篠山彦十郎
- 同九兵衛(彦十郎いとこか) 同弥次兵衛(彦十郎子)
- 梅田勝右衛門
- 柘榴勘右衛門 梅田武左衛門(勝右衛門子)
- *城より出る衆
- 福屋津之介
- 望月加左衛門(津之介子)
- 望月助遣
- 同六右衛門(助遣子)
- 山中五郎左衛門
- 同五郎左衛門(五郎左衛門子) 同次左衛門(養子)
- *道阿弥より入れし衆
- 和田太兵衛
- 同新平(太兵衛子)
- 滝喜兵衛
- 同久太夫(喜兵衛子)
- 山岡新介
- 同伝左衛門(新介おい)
- (復元者追記)頭書の人物が籠城戦に参加した者(和田は道阿弥とともに関東に行く)
次以降に記載の人物はその跡継ぎ(参加者子)及び後見人・補佐人であると思われる。
<本家系図より>
*討死と付記している者
景春 景尚 竹林景初(左衛門九郎、景春の父のいとこ) 竹林景吉(左衛門九郎の子) 景次(竹林薩摩、景吉の弟)
景春 景尚 竹林景初(左衛門九郎、景春の父のいとこ) 竹林景吉(左衛門九郎の子) 景次(竹林薩摩、景吉の弟)
- 注1:
- 伏見籠城覚の篠山彦十郎にある九兵衛は景春の弟資重かその子資吉であり、共に久兵衛という。彦十郎の叔父かいとこに当たる。系図には記録がないが資重親子が討死したのかもしれない。尚、弥次兵衛は彦十郎の子であり景末のこと。但し討死していない。
- 注2:
- 同じく竹林左衛門佐にある権兵衛は景吉の子景盛の事、系図には討死の記録はない。
*景春の項に
「〜鳥井彦右衛門元忠以下戦死而景春父子與竹林高嶺梅田上野等譜代家士中村作右衛門其他31人討死畢〜」
「〜鳥井彦右衛門元忠以下戦死而景春父子與竹林高嶺梅田上野等譜代家士中村作右衛門其他31人討死畢〜」


