
篠山十兵衛景義
大坂代官の任務は、一般の年貢徴収のほか、とくに全国の直轄領から西回り開運によって集ってくる城米の船改めが重要な仕事であった。
さて大坂代官役所については、鈴木町と谷町の二個所にあり、その地位は高かった。それは大坂が江戸に次ぐ重要な直轄都市であったからである。そのため有能な代官を、特に大坂代官に任命するケースが多く、大阪における行政手腕が評価されると、次に関東地回り代官を経て昇進する場合が見受けられた。中には年貢の増徴のみに走って成績をあげる代官もいたが、「近来、有徳の代官死して後、土民その墓を作り、碑を建て、或いは叢祠を建て祭ることあり。」(松屋筆記)と、代官の事績を評価する碑や社が多く見られることを記している。
大阪市浪速区本町2丁目に、難波八坂神社がある。この神社はスサノウノミコト、クシナダヒメ、八柱御子命を祭神とし、江戸時代は大社であった。神社は昭和20年、空襲で焼けたが、市民の尽力で復旧した。
大鳥居をくぐって社務所玄関の西側に篠山神社がある。大坂代官篠山十兵衛景義の遺徳を顕彰するために明治13年に創建されたものである。顕彰碑の表には
世の人の あふくもたかき功こそ 巌とともに朽ちせざりけれ
と刻まれてある。その裏には、
「野菜の市ができたのは、文化の頃であるが、これは簡単にできたのではない。この地の人々が嘆訴を重ね、それを篠山代官が受け入れて力を尽くしてくれたからである。村民は父母のように仰ぎ、追慕して今日に至る。碑を建てて不朽に伝えよう。」
という意味の言葉が書かれている。
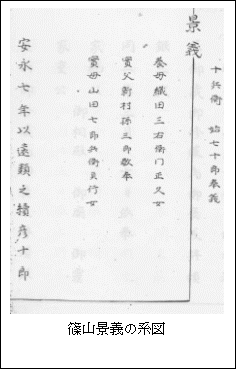
この景義は、宝暦5年に新村孫三郎数奉の次男として生まれ、のち甲賀組の与力篠山彦十郎景定の養子となっている。安永9年(1780)26歳のとき勘定吟味方改役並、32歳には勘定吟味方改役となり、天明8年(1788)には勘定に昇進している。会計に精通していたのであろう。
代官に任じられたのは34歳のときで、下野国の東郷、陸奥国小名浜、栃木の真岡の代官を歴任し、寛政5年(1793)に大坂の鈴木町代官所へ転勤を命じられた。これから文化6年までの16年間の長期在勤は特筆すべきものである。支配領域は摂津・河内・播磨の三ヶ国240村に及んだ。
代官に任じられたのは34歳のときで、下野国の東郷、陸奥国小名浜、栃木の真岡の代官を歴任し、寛政5年(1793)に大坂の鈴木町代官所へ転勤を命じられた。これから文化6年までの16年間の長期在勤は特筆すべきものである。支配領域は摂津・河内・播磨の三ヶ国240村に及んだ。
ところで、大阪では堂島の米市場とともに天満の青物市場、雑候場の魚市場がある。そのうちの天満の青物市場は、幕府の保護によって独占市場になっていて、木津・難波の地域では生産農民自身が青物の直接販売をすることができない状況だった。「立ち売り許可」はこの地方村民の永年の願いであり、幾度も嘆願書を出している。そして、篠山代官がこの願いを受けとめて尽力した結果、ようやく公認の運びとなったのである。難波や木津の発展に一つの契機を与えたといえよう。
景義は文化6年(1809)、江戸近郷の地回り代官となり、翌7年、勘定吟味役に昇進している。その後、日光東照宮の修復や家康の200年忌法要御用など務め、13年(1816)に佐渡奉行に就任している。しかし、在任わずか10ヶ月で病死した。齢63歳であった。墓は佐渡の青岳山総源寺に「墓碑銘」とともにある。(同成社 村上直著 「江戸時代の代官群像」による。)


