
戦国時代に始まった篠山氏は、初代の景春、2代の景尚の戦死により危機を迎えるが、家督は景尚の弟である資盛に譲られ、江戸時代を通じて旗本として継続する。鳥居野を知行した資盛の系統や戦死した景尚の系統について代を追って解説する。
1 資盛の系統
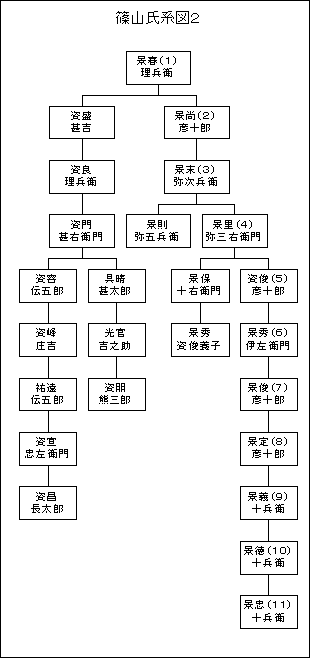
* 資盛
「資友、甚吉、理兵衛。今の呈譜初資友のち資盛また資俊につくる。母は某氏。慶長5年関ケ原凱旋ののち召されて東照宮に拝謁し、伊勢の国の御代官となり、のち羽柴下総守雄利が伊勢国神戸城岡本下野守家憲が同国亀山城を没収せらるるのとき、彼地に至り城請取りのことを勤む。其後御上洛に供奉し伊勢国にをいて放鷹したまふのとき御鷹野ゆがけをたまふ。其のち職をゆるされ、大坂両度の御陣にしたがひたてまつり、寛永2年10月23日近江国甲賀郡のうちにして采地480石を宛行はるるのむね御判物を下さる。3年大番に列し、10年2月7日相模国大住郡のうちにをいて新恩200石をたまふ。12年2月2日死す。年60。法名了和。葬地近江国甲賀郡鳥居野村の大善寺に葬る。妻は三好因幡守一任が女。」(寛政重修諸家譜)
資盛が勢州の代官となったのは関ケ原の役直後で、それは父景春の職を継いだものであるが、鳥居野に所領480石を認められたのは寛永2年(1625)となっている。甲賀郡の土地支配は甲賀53家などという地侍が父祖伝来の地としていたが、先に述べたように秀吉に没収され、それが家康の直轄地として幕府領になっていたと思われる。元に復するのに25年の歳月を要したのである。この480石は幕末に至るまで篠山氏(300石と180石)の石高として続いている。
なお、大善寺と記されているが、所在不明。多聞寺の誤りか。
(復活者追記)篠山氏の菩提寺は元々大善寺であったようであるが、同寺が破却されたため菩提寺を多門寺に変更した模様。(略譜より)
(復活者追記)篠山氏の菩提寺は元々大善寺であったようであるが、同寺が破却されたため菩提寺を多門寺に変更した模様。(略譜より)
* 資良
次の資良は上総国に450石の采地があったが、寛永12年に家督を継いで、これまでの采地は収められている。明暦元年(1655)に死亡。葬地は江戸牛込の鳳林寺。これまでの領主は鳥居野の大善寺(資料のまま)であったが、この代から江戸になる。
* 資門
次代の資門は、通称甚右衛門といいお姫山の笠塔婆の主である。寛政重修諸家譜には、
「慶安2年3月3日はじめて厳有院殿(家綱)に拝謁す。時に9才。明暦元年12月5日遺跡を継ぎ、小普請となる。3年6月20日大番に列し、延宝4年(1676)5月7日組頭に進み、天和2年4月22日200俵の加恩あり。元禄6年6月26日務めを辞す。10年7月26日廩米(扶持米)を采地に改められ下総国岡田郡のうちにおいて200石をたまふ。のち岡田郡の采地を同国香取郡の内にうつさる。16年7月22日致仕し、宝永2年(1705)5月15日死す。年65。法名宗肝。葬地資良に同じ。妻は松平豊前守勝義が女。」
長々と引用したが、これはお姫山の石碑との対照をしたかったのと、この頃の采地がこのように各地に散らばっていたこと、篠山氏が鳥居野だけでなく他の地域でも采地を持っていたこと等を具体的に示したかったからである。(お姫山の項参照)
資門に続いて具晴(ともはる)、光官(みつのり)、資朋(すけとも)と続く。簡単に記す。
* 具晴
甚太郎。資門の子。延宝4年、初めて家綱に拝謁。時に7才。
元禄4年御小姓組の番士に列し、16年家督を継ぐ。500石を知行し、弟伝五郎資容に380石の地を分かち与える。
宝永2年妻のゆかりで寄合になされ、その番を許される。
元文5年(1740)死ぬ。年71。
妻は甲府の家臣越智與右衛門の娘。大鳥神社本殿前の灯籠の寄進者である。石灯籠には「元禄11戊寅年11月吉日 祇園社御宝前奉寄進石灯両基越知氏女資章妻」と書かれている(大鳥神社の項参照)。資章は具晴の別名と考えられるが断定は差し控える。
元禄4年御小姓組の番士に列し、16年家督を継ぐ。500石を知行し、弟伝五郎資容に380石の地を分かち与える。
宝永2年妻のゆかりで寄合になされ、その番を許される。
元文5年(1740)死ぬ。年71。
妻は甲府の家臣越智與右衛門の娘。大鳥神社本殿前の灯籠の寄進者である。石灯籠には「元禄11戊寅年11月吉日 祇園社御宝前奉寄進石灯両基越知氏女資章妻」と書かれている(大鳥神社の項参照)。資章は具晴の別名と考えられるが断定は差し控える。
- (注)
- 「資章」の名が記されているのは、篠山本家筋の系図のみである。ここには、資門の子に具時と資繁の二人がおり、具時の子に資章が書かれている。しかし、寛政諸家譜では資門が家督を譲り具晴が家督を継いだのは元禄16年7月22日と記されており、妻が越智氏の娘であることも明白である。
* 光官
吉之助。具晴の子。元文5年、遺跡を継ぎ、寄合に列し、吉宗に拝謁。明和6年御徒の頭[1]となり、布衣[2]を着すことを許される。安永2年西城のお目付けに転じ、4年西城御先弓の頭に移り、8年より本城に勤仕する。天明7年新番の頭にすすみ、寛政2年(1790)年75才で死ぬ。
* 資朋
熊三郎。光官の養子。天明7年家斉に拝謁。寛政2年遺跡を継ぐ。25才、采地500石。御書院の番士[3]に列す。
2 資容の系統
* 資容
傳五郎 篠山甚右衛門資門の次男 母は松平豊前守勝義の娘
貞亨2年3月朔日初めて常憲院殿(綱吉)に拝謁する。(時に7歳)。元禄16年7月22日父の采地近江国甲賀、下総国香取両郡のうちにおいて380石を分かち与えられ小普請となる。12月4日大番に列し享保9年10月9日新番に転じる。11年正月10日死す。年48歳。牛込の鳳林寺に葬る。
貞亨2年3月朔日初めて常憲院殿(綱吉)に拝謁する。(時に7歳)。元禄16年7月22日父の采地近江国甲賀、下総国香取両郡のうちにおいて380石を分かち与えられ小普請となる。12月4日大番に列し享保9年10月9日新番に転じる。11年正月10日死す。年48歳。牛込の鳳林寺に葬る。
* 資峯
政武 庄吉 下嶋彦五郎政友の次男 資容の娘の養子。
享保11年4月5日遺跡を継ぎ12年4月11日新番に列し、18年6月14日死す。年25。
享保11年4月5日遺跡を継ぎ12年4月11日新番に列し、18年6月14日死す。年25。
* 祐遠
金弥 傳五郎 下嶋彦五郎政友の6男 資峯の養子。
享保18年9月2日遺跡を継ぎ延享3年6月15日初めて惇信院殿(家重)に拝謁する。寛延元年西城の御腰物方となり、2年に新番に転じ、宝暦6年9月27日死す。年40。
享保18年9月2日遺跡を継ぎ延享3年6月15日初めて惇信院殿(家重)に拝謁する。寛延元年西城の御腰物方となり、2年に新番に転じ、宝暦6年9月27日死す。年40。
* 資宣
銕太郎 忠左衛門
宝暦6年閏11月3日遺跡を継ぎ、明和5年正月19日大番となり、安永9年番を辞し、天明5年3月29日死す。年46。
宝暦6年閏11月3日遺跡を継ぎ、明和5年正月19日大番となり、安永9年番を辞し、天明5年3月29日死す。年46。
* 資昌
長太郎 伊織
天明5年3月29日家を継ぎ、(時に20歳、采地380石)8年大番に列し、寛政2年番を辞し、10年新番となる。
天明5年3月29日家を継ぎ、(時に20歳、采地380石)8年大番に列し、寛政2年番を辞し、10年新番となる。
* 資銕
長太郎
3 景尚の系統
次に景尚の子孫について述べる。多聞寺にある墓は慶長5年の伏見城籠城で討死にした篠山家10士の墓である。景尚の子は幼児のため鳥居野の采地などの家督は弟の資盛に移ったが、家康は本家筋にも配慮をしている。以下代を追って記す。
(復元者追記)多聞寺の墓(石碑)は篠山に付き従った地侍10人のものであると思われる。なお、この家系が鉄炮百人組の甲賀組で与力を勤めた家系である。
(復元者追記)多聞寺の墓(石碑)は篠山に付き従った地侍10人のものであると思われる。なお、この家系が鉄炮百人組の甲賀組で与力を勤めた家系である。
* 景尚(2代)
景春の子。彦十郎のこと。慶長5年父と一緒に伏見城名古屋丸で討ち死にする。
* 景末(3代)
景尚の子。弥次兵衛と称し弓が上手だった。父討死以後蟄居していたが関ケ原の戦いも終わって召し出され、父の武勇を褒められ田堵野村200石、地侍10人200石を賜う。寛永9年家光公に拝謁。江戸の桜田御門番や水口城に在番。寛永19年没。別の資料によると、江戸青山の甲賀町に居住し、知行200石としている。景末の代から江戸に移ったものと思われる。
* 景里(4代)
景末の子。弥三右衛門と称す。寛永20年水口城勤めから江戸大手三御門番に代わる。万治4年没。
* 資俊(5代)
景里の子。彦十郎と称す。家綱が日光山御社参の時お供をしている。享保9年没。
* 景秀(6代)
資俊の弟資保の長男。元禄13年資俊の養子となり伊左衛門と称す。吉宗が日光御社参のおりお供をしている。寛保3年没。
* 景俊(7代)
通称彦十郎。寛延4年没。
* 景定(8代)
通称彦十郎。所領230石余が田堵野村にあったが遠国のため難渋し、「甲賀組一統奉願可下賜現米80石之旨寛延3年5月2日於御蔵下賜現米80石畢」。文化4年没。
* 景義(9代)
通称十兵衛。実父新村孫三郎。安永7年に親類の縁で景定の養子となる。
百人組[4]の与力を勤め、勘定方吟味役となって関東及び伊豆の川普請などに努めた。その後、堤奉行廻船改、関東地回り支配、五畿内筋支配などの役職についている。
大阪の西成代官としては寛政5年(1793)から文化6年まで16年間に及び、住民に慕われ、篠山神社の祭神[5]と崇められている。また、役替えの報があったとき、引き続いて在役してほしいとの願い(「今暫御在役願書」)を管下の郡総代や庄屋が連署し、老中土井利厚に差し出している。在任中に天満に独占されていた青物市場を難波木津のも開設できるよう尽力したからである。文化6年には「被命関東地回り支配8万石高御役料下賜300俵…」であった。
文化13年10月佐渡奉行となり翌文化14年佐渡相川官邸にて没す。享年63才。青岳山総源寺に葬られる。(詳しくは別記)
百人組[4]の与力を勤め、勘定方吟味役となって関東及び伊豆の川普請などに努めた。その後、堤奉行廻船改、関東地回り支配、五畿内筋支配などの役職についている。
大阪の西成代官としては寛政5年(1793)から文化6年まで16年間に及び、住民に慕われ、篠山神社の祭神[5]と崇められている。また、役替えの報があったとき、引き続いて在役してほしいとの願い(「今暫御在役願書」)を管下の郡総代や庄屋が連署し、老中土井利厚に差し出している。在任中に天満に独占されていた青物市場を難波木津のも開設できるよう尽力したからである。文化6年には「被命関東地回り支配8万石高御役料下賜300俵…」であった。
文化13年10月佐渡奉行となり翌文化14年佐渡相川官邸にて没す。享年63才。青岳山総源寺に葬られる。(詳しくは別記)
* 景徳(10代)
初名守四郎光徳、後、十兵衛と称す。実父は木村周蔵光休。
文化5年に景義の養子となり天保5年御徒頭、同7年佐渡奉行。天保9年8月、佐州百姓騒乱があり、これを鎮めた。「8月2日被佐州百姓共就騒立為吟味被差遣但就御序無之不能拝謁之旨於芙蓉間以老中太田備後守資始被伝厳・・」(系図)と書かれている。
同11年御先鉄砲頭を命じられ、同13年家慶公日光山御社参の供を命じられる。天保14年には従5位下に叙されている。天保15年10月、御本丸炎上の節「早速罷出指図に及び骨折り一段の事之旨老中阿部伊勢守正弘演達」。弘化2年御本丸御普請御用格別骨折り出精につき300石御加恩。
嘉永5年3月15日には大目付[6]、安政2年には御槍奉行となる。安政3年2月17日没す。
文化5年に景義の養子となり天保5年御徒頭、同7年佐渡奉行。天保9年8月、佐州百姓騒乱があり、これを鎮めた。「8月2日被佐州百姓共就騒立為吟味被差遣但就御序無之不能拝謁之旨於芙蓉間以老中太田備後守資始被伝厳・・」(系図)と書かれている。
同11年御先鉄砲頭を命じられ、同13年家慶公日光山御社参の供を命じられる。天保14年には従5位下に叙されている。天保15年10月、御本丸炎上の節「早速罷出指図に及び骨折り一段の事之旨老中阿部伊勢守正弘演達」。弘化2年御本丸御普請御用格別骨折り出精につき300石御加恩。
嘉永5年3月15日には大目付[6]、安政2年には御槍奉行となる。安政3年2月17日没す。
* 景忠(11代)
文政11年家斉公に拝謁。天保12年両御番西丸御書院番となる。
<甲賀郡志の所領記述について>
郡志上巻第6編第6節鳥居野の項には、「…天正年間徳川氏の所領となり、元和元年に至り3分せらる。即、一は篠山甚吉郎(大原源三の末流)の采邑となり、一は寛永2年弟篠山忠三郎に属し一は同10年水口城代小堀遠江守の治下に属し、以後…」と書かれている。
この中の甚吉郎は、この資盛のことと思われるが、弟忠三郎は、不明。元和元年の資料も不明である。知行を弟に分かち与えたのは具晴の時で、元禄16年(1703)に家督を継ぎ、500石を知行し、内380石を弟伝五郎資容に分けたのである。その後子孫が相継いで相続しており、幕末の頃、篠山彦十郎領、篠山隼人領、堀田主膳領がある。
この中の甚吉郎は、この資盛のことと思われるが、弟忠三郎は、不明。元和元年の資料も不明である。知行を弟に分かち与えたのは具晴の時で、元禄16年(1703)に家督を継ぎ、500石を知行し、内380石を弟伝五郎資容に分けたのである。その後子孫が相継いで相続しており、幕末の頃、篠山彦十郎領、篠山隼人領、堀田主膳領がある。
<佐渡の国天保9年一揆>
1831(天保2年)以来打ち続く凶作に佐渡の農民が免訴を願い出たが、奉行所は顧みなかった。上山田村の善兵衛は奉行所たのむにたらずとし、時機を待った。
たまたま38年(天保9年)将軍交代の御料所巡見使が渡島する触出があった。善兵衛は、同士村山村神官宮岡豊後ら数名と図り佐渡奉行所のひ政、地役人の悪習、農民の窮状を数カ条にしたため(内容不明)、訴状を作って巡見使を待った。
巡見使広木義太郎らは4月19日小木港へ到着、島内の巡見を終えて5月2日に佐渡を去ったがこの間に道中で訴状を提出され受理した。次いで甲使巡見使木下内記らが5月13日来島、巡見回村中に善兵衛らは更に二個条を追加して村山村市右衛門の名を以て提出した。
奉行鳥居八右衛門は地役人に命じて、昨春大塩の乱のこともあり、農民に徒党の禁を犯さないことを諭し、善兵衛を召喚して事情をただそうとしたが、善兵衛が応じないので小木で捕らえて相川まで引き立て、取り調べたが黙秘しているのでやむなく投獄した。
宮岡らはこれを不服として八幡宮社前に一万余の農民を集めて奉行所を襲い、善兵衛を奪い還そうとした。
奉行所は驚いて直ちにこれを弾圧しようとしたが、地役人井口方義は農民の感情を察し、事の拡大を恐れ、善兵衛を釈放したのでいちじ事無くすんだ。
しかし、農民はかえって勢いに乗じて5月24日八幡村名主四郎吉宅を襲撃したのを始めとし、各地に問屋富豪を襲い、8月に入っても暴動が止まず、奉行所はその都度首謀者を捕らえて投獄した。
8月篠山十兵衛奉行は高田藩兵200人を率いて相川につき、直ちに善兵衛ら7人を捕らえて糾明すると、地役人の姦曲が一揆の原因たることを知り、地役人7人を揚屋入りとし翌年3月審理を江戸奉行に引き渡した。
江戸へ送られた地役人、農民12人は伝馬町の獄にあるうちに、多くは病死して、判決は翌11年6月に延びた。役人側では佐渡奉行2人差控となったほか64人が処罰され、農民側では善兵衛が獄門、宮岡豊後の死罪をはじめ遠島三人その他86人処刑、また連帯で村高に応じて過料に処せられたもの二百数十か村に及んだ。この一揆は首謀者は極刑を受けたが、地役人の不正が正されたので一揆の目的はなかば達した。(日本歴史大事典 河出書房)
たまたま38年(天保9年)将軍交代の御料所巡見使が渡島する触出があった。善兵衛は、同士村山村神官宮岡豊後ら数名と図り佐渡奉行所のひ政、地役人の悪習、農民の窮状を数カ条にしたため(内容不明)、訴状を作って巡見使を待った。
巡見使広木義太郎らは4月19日小木港へ到着、島内の巡見を終えて5月2日に佐渡を去ったがこの間に道中で訴状を提出され受理した。次いで甲使巡見使木下内記らが5月13日来島、巡見回村中に善兵衛らは更に二個条を追加して村山村市右衛門の名を以て提出した。
奉行鳥居八右衛門は地役人に命じて、昨春大塩の乱のこともあり、農民に徒党の禁を犯さないことを諭し、善兵衛を召喚して事情をただそうとしたが、善兵衛が応じないので小木で捕らえて相川まで引き立て、取り調べたが黙秘しているのでやむなく投獄した。
宮岡らはこれを不服として八幡宮社前に一万余の農民を集めて奉行所を襲い、善兵衛を奪い還そうとした。
奉行所は驚いて直ちにこれを弾圧しようとしたが、地役人井口方義は農民の感情を察し、事の拡大を恐れ、善兵衛を釈放したのでいちじ事無くすんだ。
しかし、農民はかえって勢いに乗じて5月24日八幡村名主四郎吉宅を襲撃したのを始めとし、各地に問屋富豪を襲い、8月に入っても暴動が止まず、奉行所はその都度首謀者を捕らえて投獄した。
8月篠山十兵衛奉行は高田藩兵200人を率いて相川につき、直ちに善兵衛ら7人を捕らえて糾明すると、地役人の姦曲が一揆の原因たることを知り、地役人7人を揚屋入りとし翌年3月審理を江戸奉行に引き渡した。
江戸へ送られた地役人、農民12人は伝馬町の獄にあるうちに、多くは病死して、判決は翌11年6月に延びた。役人側では佐渡奉行2人差控となったほか64人が処罰され、農民側では善兵衛が獄門、宮岡豊後の死罪をはじめ遠島三人その他86人処刑、また連帯で村高に応じて過料に処せられたもの二百数十か村に及んだ。この一揆は首謀者は極刑を受けたが、地役人の不正が正されたので一揆の目的はなかば達した。(日本歴史大事典 河出書房)
- [1]御徒の頭・・・
- 徒組は将軍の出向に先駆けて行く手の道路の警戒にあたる。20組あり、各組一人の徒頭、二人の組頭、30人の組衆がいた。
- [2]布衣・・・・・
- 江戸時代目見(将軍に謁見できる)以上の者が着る服。また、その資格。
- [3]書院番・・・・
- 戦時には小姓組と共に将軍を守り平時は中雀門の他本丸の主要な門を固めた。
- [4]百人組・・・・
- 甲賀組、根来組、伊賀組、25騎組の4組あり、いずれも同心百人ずついるので百人組という。同心の上の与力は各組20人(25騎組は25人)。大手三門の守備をする。
- [5]篠山神社・・・
- 大阪難波八坂神社境内にある神社
- [6]大目付・・・・
- 老中の耳目となり大名等を監察した。普段の仕事は大名居城の修理を監視し、将軍の行列を監督した。職掌柄大名の待遇を受けた。今日の検事総長にあたる。

